食物繊維と聞くと、「おなかの調子を整える成分」といったイメージを持つ方も多いと思います。
食物繊維には「不溶性」と「水溶性」の2種類があり、実はそれぞれが体に与える働きは異なります。
便通を改善する、血糖値の上昇をゆるやかにする、コレステロールを減らすなど、「食物繊維をとることで得られるとされる健康効果」も、どのタイプの食物繊維を摂るかによって変わってきます。
この記事では、不溶性食物繊維と水溶性食物繊維の違いや特徴、摂り方などについてわかりやすく解説していきます。健康な腸内環境を維持するために、食物繊維について知識を深めましょう!
食物繊維とは?
まず、食物繊維とは「ヒトの消化酵素で分解されない食物中の総体」と定義されています。つまり、人間の体内で消化吸収されずに腸まで届く成分です。
食物繊維は植物性食品に多く含まれ、「第6の栄養素」とも呼ばれる重要な栄養成分です。
食物繊維は大きく分けて「不溶性食物繊維」と「水溶性食物繊維」の2種類があり、それぞれ異なる特徴と効果を持っています。
不溶性食物繊維と水溶性食物繊維の基本的な違い
不溶性食物繊維
不溶性食物繊維は水に溶けない性質を持つ食物繊維です。繊維質でボソボソとした形状が特徴で、主に植物の細胞壁などに含まれています。一般的に「便のカサを増やす繊維」として知られています。
水溶性食物繊維
水溶性食物繊維は水に溶ける性質を持つ食物繊維です。腸内では主に「便を柔らかくする繊維」として働きます。
不溶性食物繊維の特徴と効果
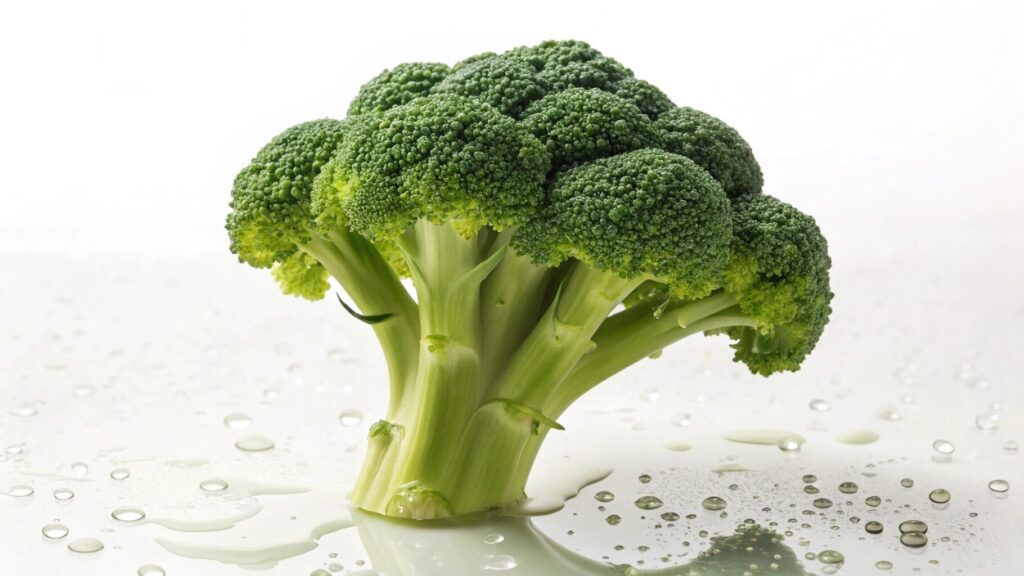
主な効果・作用
- 保水性が高く、水分を吸収して大きくふくらみ、便のかさを増やす
- 腸を物理的に刺激して蠕動(ぜんどう)運動を活発にする
- 便通を促進し、便秘の予防・改善に効果的
- 腸内の有害物質を吸着して排出するデトックス作用
- 便と一緒にコレステロールを体外へ排出する働きも
不溶性食物繊維の代表例
セルロース、ヘミセルロース、リグニンなど
不溶性食物繊維の特徴
繊維状、ボソボソ、ザラザラとした食感
不溶性食物繊維が多く含まれる食品
穀類
- 玄米
- 全粒粉
- ライ麦
- そば
野菜類
- ごぼう
- かぼちゃ
- ブロッコリー
- かんぴょう
その他
- 大豆・豆類
- きのこ類(しいたけ、きくらげ)
- 果物の皮
水溶性食物繊維の特徴と効果

主な効果・作用
- 水に溶けてゲル化し、食後の血糖値の急激な上昇を抑制
- 腸内で善玉菌のエサとなり、腸内環境を整える
- コレステロールやナトリウムの吸収を阻害し、血中コレステロール値を低下させる
- 腸内細菌によって発酵し、短鎖脂肪酸を増やす
- 便を柔らかくして排泄を促進
水溶性食物繊維の代表例
ペクチン、グアガム、アルギン酸、β-グルカンなど
水溶性食物繊維の特徴
ネバネバ、サラサラした状態になり、水に溶けるとゲル状になる
水溶性食物繊維が多く含まれる食品
海藻類
- わかめ
- 昆布
- もずく
- 寒天
果物・野菜
- りんご
- 柑橘類
- オクラ
- 春菊
その他
- 大麦(押麦)
- オートミール
- こんにゃく
- さつまいも
不溶性と水溶性の比較
| 不溶性食物繊維 | 水溶性食物繊維 | |
|---|---|---|
| 水への溶解性 | 水に溶けない | 水に溶ける |
| 主な作用 | 便のかさを増やし、腸の蠕動運動を促進 | 血糖値の上昇抑制、善玉菌の増加 |
| 特徴 | ボソボソ、ザラザラ | ネバネバ、ゲル状 |
| 代表的なもの | セルロース、ヘミセルロース、リグニン | ペクチン、グアガム、アルギン酸 |
| 代表的な食品 | 玄米、ごぼう、豆類、きのこ類 | 海藻、りんご、オクラ、大麦 |
食物繊維の推奨摂取量
厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2025年版)」によると、食物繊維の目標摂取量は以下のとおりです。
成人男性(18~64歳)
21g以上/日
成人女性(18~64歳)
18g以上/日
不溶性と水溶性のバランス
食物繊維を摂取する際には、不溶性と水溶性をバランスよく摂ることが大切です。理想的な比率としては、不溶性:水溶性 = 2:1とされることが多いですが、両方をまんべんなく摂ることを意識しましょう。
食物繊維を効率よく摂取するために、日常生活で実践できること
- 主食を精製度の低いものに変える(白米→玄米・麦ごはん、食パン→全粒粉パン)
- 野菜は生よりも加熱調理して量を確保する
- 野菜や果物は皮ごと食べられるものは皮も一緒に摂る
- 汁物に海藻やきのこを積極的に加える
- 食事の最初に野菜から食べる順序を意識する
まとめ
不溶性食物繊維と水溶性食物繊維はそれぞれ異なる特性と健康効果を持っています。
健康な腸内環境を維持するためには、両方をバランスよく摂取することが大切です。
不溶性食物繊維は便のかさを増やして便通を改善し、水溶性食物繊維は血糖値の上昇を抑制したり腸内の善玉菌を増やしたりします。これらの作用は相互に補完し合い、全体として腸内環境を整える効果をもたらします。
さまざまな植物性食品をバランスよく摂ることで、自然と両方の食物繊維を摂ることができます。毎日の食事で意識して取り入れ、健康的な腸内環境を目指しましょう。



